なぜ年を取ると足がつりやすくなるのか?
足のつりは、医学用語では「有痛性筋痙攣」(けいれん)といいます。簡単に言うと「こむら返り」です。
筋肉は、伸びすぎても縮み過ぎても機能を失ったり傷ついてしまう恐れがあります。
そうならない為に2つのセンサーがあります。
① 筋紡錘(きんぼうすい)
ふくらはぎの筋肉が伸びすぎてしまった時に、一定のところまで行くとセンサーが働き筋肉を縮ませて元に戻すような指令を脊髄から送ります。それにより筋肉が痛まないようにしています(ストッパーの役割)。
脊髄反射という言葉の通り、意思に関係なく起こります。
② 腱紡錘(けんぼうすい)
腱紡錘は筋紡錘と反対の働きをしています。
筋肉が縮み過ぎた時にセンサーが働き筋肉を元に戻します。
筋紡錘と腱紡錘によって知らないうちに、筋肉がしなやかに傷つかずにバランスをとってくれています。
腱紡錘の機能が働かないと、筋肉が縮んだまま戻らなくなってしまい「こむら返り」が起こります。
足がつる病気
①糖尿病
糖尿病によって神経の回路にダメージを与えることで足がつりやすくなります。毎日足がつってしまう人もいます。血液検査をすると血糖値が高くなっているかもしれません。
②脊髄の病気
ふくらはぎは脊髄から指令が送られて伸び過ぎたり縮み過ぎたりしないように管理されています。
しかし、この脊髄に障害が起きてしまうと間違って筋肉を縮めたりします。
腰椎椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症などは、ふくらはぎの筋肉を縮めてしまい足がつる原因になることがあります。
●なごみ整骨院では、足や足関節・股関節・腰・背中など‥時間をかけて、他では受けられない施術をし改善しますので早めにお越しください。
③足の血管の病気
①閉塞性動脈硬化症(ASO)
足の血管の病気で、動脈が硬くなります。
②下肢静脈瘤
足の血管の病気で、静脈血が戻りにくくなります。
④その他の病気
肝臓病や腎臓の病気の人、特に人工透析をしている人に起こりやすくなります。
どういう時に病院へ行ったらいいのか?
こむら返りが起こる頻度が多い場合は、早めに病院は行って検査を受けましょう。
歩いていたり、走っていた時に急にふくらはぎが痛くなった時は、「間欠性跛行」といって神経の障害や血管の障害などで起こることがあります。これは「脊柱管狭窄症」や「閉塞性動脈硬化症(ASO)」の可能性がありますので病院で検査を受けましょう。
加齢と足のつりの関係
今まで書いてきたように糖尿病・脊髄の病気・足の血管の病気などが関係していますが、最も関係が深いのが「筋肉量が減ってしまう」ことです。
若い人では、サッカーやランニングなど激しい運動をし過ぎた時以外はほとんど起こりません。
しかし、筋肉量が減ってきた高齢者は以前より少しのことがきっかけで筋肉のバランスが崩れてしまい、こむら返りが起きてしまいます。
その他、水分やミネラルの調節が以前よりうまくできなくなっています。
例えば、熱中症で足がつった場合、脱水や汗が出ることによる「ナトリウム不足」が関係しています。
若い人は、熱中症にならないと起こらないことが多いのですが、年を取ってくると水分などの調節能力が落ちているので起こりやすいくなります。
高齢者は、睡眠の終わりがけに脱水気味になり足がつってしまうこともあります。
対策は?
筋肉量が減っていくことが足のつりにつながりやすいので、普段から「ウォーキング」や「ランニング」や「水泳」など、足の運動をしておいてください。
いくつになっても運動や筋トレをしていけば、筋肉はだんだんとついてきますのであきらめなくても大丈夫です。
寝ている時の足のつりに関しては、水分量が減ると起こりやすいので、寝る前に水分を適度にとってください。
ただ、水分をとり過ぎるとトイレが近くなってしまいますので、のどがカラカラにならない程度に調整してください。
また、冷えると足の筋肉は縮みやすくなりますので温めておくことも大切です。
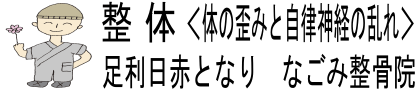





お電話ありがとうございます、
なごみ整骨院でございます。